
日本環境変異原ゲノム学会
The Japanese Environmental Mutagen
and Genome Society (JEMS)

日本環境変異原ゲノム学会
The Japanese Environmental Mutagen
and Genome Society (JEMS)
2003年5月30日の編集・広報合同委員会において応募されたロゴを審査した結果、石井 裕会員より応募された作品が、グランプリとして選ばれました。それに引き続いて開催された理事会、評議員会において、今後このロゴを日本環境変異原学会のロゴとして使用することが決定されました。
新しいロゴとロゴの意味するところは以下の通りです。
グランプリ受賞作品
2つのデザインのうち、左の方は背景が白地の場合のもの、右の方は表紙が赤・黒などの色地の場合に使用します。
審査員特別賞受賞作品
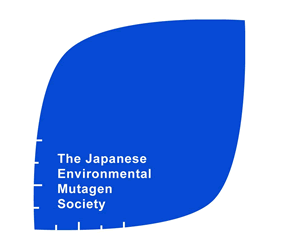
コンセプトが「あらゆるタイプの線量-効果曲線の集合体を青でシンボライズされ、左辺、底辺の白線は目盛りを表すという、非常に変異原学会らしいロゴであることから、「審査員特別賞」となりました。